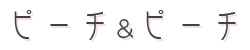
千石さんとの約束を放課後に控えた木曜日、外は清々しい快晴。
放課後は何処に行こうか、胸を踊らせながら家を出てから約30秒。
俺の頭の中で巡っていたデートスポット候補は全く役に立たない事を告げる合図は賑やかな着信音だった。
ディスプレイに表示された恋人の名に喜びと共に過る疑問。
珍しい時間の、千石さんからの電話だった。
「もしもし!千石さん?どうしたんすか?」
「……桃城くん、おはよ、朝からゴメンね……」
声を聞いた時点で様子がおかしいのはわかった。
声に張りがなく、なんとなく鼻にかかったような、そう、鼻が詰まってる時によくそうなるような声だ。
その予想は間違いではなかったようで。
「あのさ、俺、風邪引いちゃったみたいで、今日……行けなくなっちゃったんだ……ごめ、」
言い切る前に言葉を遮った咳は酷く苦しそうで、たぶん今喋るのすら辛いんだとわかる。
「大丈夫っすか?!メールとかでよかったのに……喉辛いんじゃ……」
「ん、大丈夫……今日会えなくなっちゃったからさ、声、聞きたくて……」
「千石さん……あ、じゃあ放課後見舞いとか行ってもいいっすか?」
「え……?」
一瞬、声のトーンが上がる。
「あ、でも……移しちゃうしさ、うれしーけど、やっぱ……悪いよ……うん……移したく、ない……」
それは独り言にも近い呟きだった、俺に対してよりも自分に対して言っている、言い聞かせているような、そんな印象だった。
「千石さん……」
「ああ、でも……」
ぽつりと、本当に小さく呟いたその声色は聞いたことがないほど弱々しい。
彼は精神的にとても強い。
普段は滅多なことでは弱音を吐かない。
弱味を見せない。
だからこんな声を聞いたのは本当に初めてのことだった。
「会いたかったなぁ……」
千石さんが言いたかったことはたぶん、この一点なんだろう。
そのあとすぐ、電話口から聞こえてきたのは、規則正しいとはとても言えない苦しげな寝息と衣擦れの音。
相当辛そうだったから眠ってしまったんだろうけど、電話を落としたような様子はなかった。
それはつまり彼は布団の中から俺に電話を掛けてきたわけだ。
一方的にメールで一言送れば済む内容を、力を振り絞って。
それがわかった時点で俺の決意は固まっていた。
* * *
と、決意はしたものの風邪に効く食べ物なんてあまりお世話になったことのない万年健康体のため、ぱっと思い付かない。
こんな時頼りになるのが、我が部の誇るブレーン、乾先輩だ。
俺は早速3年の教室に向かった。
「乾先輩!」
「桃城、どうした?」
「えっと、ちょっと聞きたいことがあるんすけど。風邪の時に効く食べ物とかわかります?」
「ああ、風邪にならネギ、リンゴ、蜂蜜、しょうが……」
次々と上がる食材には単体では持っていけないものも多々あるけど、見舞品の定番っぽいものもいくつかある。
「それから、甘いシロップにつけたフルーツ缶詰なども、ビタミンの吸収がしやすく、食欲の低下や喉の痛みがあっても食べやすいな」
「フルーツ缶詰……なるほど……」
大量にあげてもらった見舞品候補とその効能まで教えてもらった。
その中から頭の中で見舞品として持っていけそうなのを吟味していると、不意に俺の肩にガシッと掴む手の感触。
もちろん今俺の肩を掴めるのは一人だけ。
「え……」
「それらの効能を全て得られるこの乾汁、対風邪気味用スペシャルバージョンの試作品があるんだが、試してみるか?桃城」
あ、この流れはまずい。
「えええ遠慮しますー!!ありがとうございましたぁぁぁぁ!」
全力で頭を下げて逃亡する。
スリリング過ぎる情報収集だったけど、貰った情報は有益だった。
部活が休みなので帰り支度を終えたら直ぐ様教室を飛び出す。
チャリを飛ばして向かった先は学校から程近いスーパー。
お目当てのものを探しだし買ったら後は再びチャリを飛ばして本当の目的地へ向かった。
そして、何度か来たことのある千石さんの家へ到着したが、実は一人で訪れるのは初めてだったことに気が付く。
いつも千石さんと一緒だったから、インターフォンを押すのに妙に緊張した。
インターフォンから聞こえてきた声に答えて用件を伝えると、すぐにドアが開いた。
千石さんのお母さんと会うのは初めてじゃない。
遊びに来たときに何度か顔を合わせて挨拶したことはある。
けどそれも、いつも千石さんが傍らに居るときだった。
だからこうして、一人で対面なんて初めてのことで。
「あ、えっと、突然すみません!自分、テニス部の桃城武と申します!せんご、あっ!き、清純、さんがその、風邪って聞いてお見舞いにっ」
ああもう、一応覚悟はしてた筈なのに、なんだってこんな緊張してんだか。
これじゃあまるで恋人の家に結婚の挨拶にでも来たみたいだ。
余計なことを考えたせいで別の意味でも顔が熱くなってしどろもどろになっちまう。
呼び慣れない彼の名前を口にしたのも相まってオーバーヒート寸前の俺に千石さんのお母さんは優しく微笑みかけた。
「清純のお見舞い?わざわざありがとうね、桃城くん」
ちょっと待っててね、と言い残して、お母さんは2階に上がっていった。
一人残った玄関で失礼がなかったかとひたすら自己分析に走る。
今更ながら学校名を言わなかった事に気付いたけど、制服も違うのに突っ込まないでいてくれた事に気付いた。
「清純ー?あら起きてたの?テニス部の子がお見舞いに来てくれたけど」
上の階から様子をうかがう声が聞こえたあと、お母さんは直ぐに玄関に戻ってきた。
「今ちょうど起きてたみたい。退屈みたいだから、ぜひ会ってあげて?」
「はい!ありがとうございます」
お母さんの案内で家にあげてもらって、千石さんの部屋を目指す。
部屋の前まできて、下がろうとしたお母さんに寸前で思い出して慌てて手に持っていた袋を手渡した。
「あの、これを……っ」
「あら、わざわざお見舞い品まで、ありがとうね」
遠ざかる背中を見送ってから、俺は一度深呼吸した後扉をノックした。
中から掠れた声で返事が聞こえて、ドアノブを捻る。
「失礼しまーす」
扉から顔を覗かせると薄紅色に頬を染めた千石さんがポカンとした顔でベッドで身体を起こしてこっちを見ていた。
「……え?え!?テニス部の子って、桃城君!?なんで!?」
「えっと、朝電話貰ったじゃないっすか?あの時千石さん、今日会いたかったって言ってたから、来ちゃいました!」
「嘘!?あれ、夢じゃなかった……?あれ?俺あの時言っちゃってた!?」
どうも無意識だったらしい。
滅多に見せないであろう動揺っぷりでわたわたと顔だけ出して頭巾みたいに布団を被る。
「え?!どうしたんすか」
「だって、めちゃくちゃ汗かいてるし髪もボサボサだしパジャマだし……っ、それに風邪うつすからっ!こほっ」
慌てたせいかまた苦しそうに咳き込み出した千石さんに慌てて駆け寄って背中をさする。
「大丈夫っすか?!あんま騒いじゃ駄目ですって」
「ん……ありがと、大丈夫……っ、こほっ」
「もー大人しくしててください!」
「だって……」
「病人なんだから、格好なんか気にしなくていいんです!ほら布団ちゃんと掛けて!」
頭から被っていた掛け布団を剥いで正しく掛け直す。
よっぽど恥ずかしいのか彼はせめてとばかりに手櫛で髪を整えた。
「ていうか風邪、移っちゃうよ…っ?」
「だーいじょぶですって!俺、丈夫っすから!」
「本当に……?」
「大丈夫です!あ、でも身体しんどいっすよね……?寝てたかったらすぐ帰りますから」
「あっ、ちがっ、違うよっ」
捨てられた子犬みたいな顔って表現があるけど、今の千石さんの表情がまさにそんな感じ。
咄嗟に伸ばした腕が俺の手首を掴む。
その手がじんわりと汗ばんでて、やたら熱い。
熱はまだ高いんだろうか。
「あ、その……もうちょっと……居てほしいな……?」
いつもの飄々とした様子からしたらだいぶしおらしい。
風邪の時は心も弱るっつーし、彼も今そうなんだろう。
と、部屋の扉をノックする音に千石さんは驚いて手を離し、咳払いをする。
「ん、母さん?」
「お邪魔するわね〜、桃城君、お見舞いありがとうね」
そう言って、お母さんは俺が持ってきた桃の缶詰を二人分、器に盛って出してくれた。
「お持たせですが」
「あっ、俺の分まですみません」
「いえいえ、こちらこそわざわざありがとうね」
お邪魔しました、と微笑みながら会釈をして出ていくお母さんの背中に立ち上がって一礼する。
その後ろで小さく笑う千石さんの声に振り返ると、面白そうに笑っていた。
「あはは、こんな時でも運動部だなぁ、桃城君」
「これもう条件反射みたいなもんで……それより!これ……」
「ん、桃?缶詰のやつ?」
「飯は親御さんに作って貰ってると思ったんで、なんか甘いのが良いかなと思って。フルーツ缶詰はビタミンが摂れるとか、喉痛い時も食べやすいとかで……乾先輩の受け売りっすけど!」
選んだ理由を乾先輩から貰った情報を交えて早口に語る。
そして、極めつけはこれだ。
「で、せっかくなんで桃にしたんすよ。俺、桃ちゃんっすから!」
果たして外していないだろうか。
反応が返ってこないのが、ちょっと怖い。
少しの間きょとんとした顔で俺を見つめた後、千石さんはまた笑いだした。
「あははっ、ありがとね、桃城君」
どうやらスベってはいないらしい。
一頻り笑うと、千石さんは微笑んで俺の手元に視線を留めた。
「じゃあ、貰って良い?」
布団から腕を出そうとする千石さんを制して、フォークで小さく切り分けた一口大の桃を差し出す。
「それじゃ、口開けてください。あーん」
「えっ!?じ、自分で食べられるよ……っ」
「こういうのもたまにはいいでしょ?こんな時くらい甘えてくださいよ」
照れながら暫く考え込むように目を伏せると、千石さんは小さく頷いた。
「……ん、じゃあ、今日は甘えちゃおうかな?」
はにかむように笑うと、こっちを窺うようにおずおずと口を開けた。
口に入れた桃をゆっくり咀嚼して飲み込むと、小さな子供みたいに顔を綻ばせる。
「甘い……美味しい……」
「良かった!じゃあ次」
「ん……」
せがむように口を開ける姿が可愛らしい。
そんな調子で一口、また一口と差し出していって、千石さんが皿の中の桃を食べきって満足げに笑う。
「ごちそうさま」
その後、俺も自分の分の桃を食べ始める。
そんな俺を千石さんはにこやかに見つめていた。
「あっ、これ食べます?」
「んーん、俺は充分食べたから桃城君食べてよ」
足りなかったのか、と思って聞いてみたけどあっさり否定された。
千石さんに見詰められながら皿の中の桃を口に放り込み終わる頃には、眩しいくらいの夕日のオレンジ色が窓から射し込み間もなく日が暮れることを知らせていた。
暮れる間際の綺麗な夕焼け色はここから徐々に夜の色に変わる。
「そろそろ日が暮れるなぁ……」
千石さんが窓の外に視線を向けてそう呟く。
「そっすね……そろそろ帰らねーと」
うん、と小さく言いながら頷くと、彼は視線を俺に戻す。
「今日は風邪ひいて一日アンラッキーだと思ってたんだけどさ」
目を細めて笑う彼の顔からはもう、ほんの一時間ほど前に見せた寂しさは感じない。
「君にこんな風にお見舞い来て貰えるなら、たまには風邪も悪くないなぁ……なんてね!ねえ、また風邪引いたらお見舞い来てくれる?」
冗談めかして悪戯っぽく笑う千石さんだけど、少しだけ期待を込めてそう問われた。
その期待の意味は理解した、けど、期待通りには言ってやらない。
「なに言ってるんすか!風邪なんか引かなくてもこれくらいいくらでもしますよ。だから―」
布団の上に投げ出されていた手を掴んで両手で包む。
いつも繋ぐ掌よりも高い体温は、きっとまだ残っている熱のせいだ。
「しんどい思いなんてする必要ないっすよ。いつでも呼んでください!とんでくるんで!」
「〜〜〜っ!」
夕焼け色の部屋の中でも、その頬が朱に染まったのが見えた。
照れる俺を見てまた可愛いとか言ってからかうつもりだったんだろうけど。
俺だって可愛がられるだけじゃない、この人を可愛いと思ってる。
頼られたいって思う。大事にしたいと思うから。
本当は千石さんを苦しめるウイルスだって俺が全部引き受けたっていいんだけど。
「千石さん、キスしていいっすか?」
「そ、それはダメ……本当に移しちゃうから……今日はダメだよ……っ」
「絶対ダメ?」
「ダメ……」
そう言って頑なに突っぱねられる。
千石さんも俺の事を大事にしたいと思ってるの、ちゃんと知ってるから。
俺がそれを貰ったら、この人はきっと悲しむから。
「しゃーないっすね、じゃあ、せめて」
「……っ」
頬を両手で包んで引き寄せて、額を合わせるようにくっ付ける。
本当のキスではないけど、触れあった額からじんわりと伝わる熱を肌で感じる。
「今日はこれで、次会うときはちゃんとキスしましょう」
「うん……今日、わざわざ来てくれてありがとう」
「俺も会いたかったんで!」
そう言うと、千石さんははにかむように、嬉しそうに笑ってくれた。
こんな笑顔が見られるなら俺は地球の裏側からとんでくる事だってできちまう気がするんだ。
こんなことを言うと、キザだとか言われて笑われちまうから言わないけど。
「風邪、早く治してくださいよ……?」
「うん、治す……早く治すよ」
「治ったら遊びましょうね」
「うん」
触れ合っていた額を離してオレンジ色の髪を掻きあげて、その額にひとつ啄むようにキスをした。
―終―
2016/11/06 up