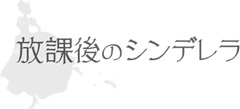
夕焼け色に染まる放課後の校舎を歩く足音が廊下に響く。
今、俺が身に纏っているのは我が校の着慣れた珍しい白い学ランではなく、上下真っ黒な正統派学ランだ。
そして俺が今歩く廊下は、通い慣れた学舎ではなく初めて足を踏み入れる校舎。
俺の指先には温かい手が繋がれていて、初めて歩く校舎の、彼が1日のほとんどを過ごす場所に導いてくれる。
俺の視界に映るのは、日々彼が見ている景色の一部。
普段の俺には共有することが出来ない日々の景色をまるで特別な魔法をかけて貰ったみたいに。
今の限られた時間だけ、俺は彼の日常の一部を共有している。
例えるなら陽が沈んだら解けてしまう、そして他の誰にも知られてはいけない秘密の魔法。
まるでシンデレラみたいだ。
なんて、ちょっとメルヘンチックな事を考えてみた。
けれどそれになぞらえて言うならば、この魔法をかけてくれたのは俺の王子様である彼本人だったりする。
今いったいどんな状況かと言うと、話は数十分前に遡る。
互いに部活のない日の放課後。
デートの約束のため青学にやってきた俺の携帯に、桃城くんからメッセージが届いた。
「……ん?」
内容はいつも待ち合わせる正門前でなく、こっそり裏庭に来てほしいと書かれていて、俺は首を傾げた。
ひとまず言われるがままにそっと校舎の裏にまわると、桃城くんが木陰に隠れるようにして手招きをしていた。
他の人に聞かれたくないんだろうと行動から察して声を潜める。
「どうしたの?」
「すみません!補習食らっちまって提出するまで帰れなくて!」
顔の前で手を合わせて頭を下げる桃城くん。
それはつまり、今日はこの後一緒に出掛けることはできないということなんだろう。
落胆しなかったかと言えば嘘になる。
けれど、彼には彼の学校生活があって、俺のために彼の学生としての生活を蔑ろにさせるわけにはいかない。
「あ、いいよいいよ!俺の事は気にしないで、補習頑張ってね」
精一杯笑ってそう言い、背を向けようとした俺の腕を桃城くんが慌てたように掴む。
「待ってくださいっ!」
「……?」
あまりの勢いに首を傾げると、桃城くんが口にしたのは意外な提案だった。
「その、教室で、一緒に待っててくれませんか?」
「え……?」
それは、彼と一緒に青学の校舎に入ると言うことで。
その誘いは俺にとって魅力的なものだけど。
「で、でも、制服違うしすぐバレちゃうよ……?」
顔よりも先に目につくだろう部外者の証。
彼の着ているそれとは明らかに違う山吹中の白い制服は誤魔化しようがない。
けれど彼は得意気に笑って言った。
「そこは考えてあるんすよ」
自分の制服を誇示するように彼は前のボタンを開けた学ランを引っ張って広げて見せる。
「これ、千石さんが着てください。伸長一緒だし着られると思います」
「え?でも君は……?」
「俺はこれがあるんで!」
桃城くんがさっきから腕に下げていた布の袋の中から、たぶん青学の学校指定のものだろうジャージを取り出して言った。
なるほど、確かにこれなら校内に居ても他校の生徒とはバレにくいかもしれない。
青学は生徒も多いし、俺の顔を知らない限りは他校生とは気付かれないだろう。
なんだか面白そうな展開に俺も乗っかって、物陰で桃城くんの制服に着替える。
「どう?似合う?」
「なんか、新鮮っすね」
そう言った桃城くんの頬が少し赤くてなんだか俺まで照れてしまった。
千石さんの髪は目立つから、そう言われて頭からタオルを被る。
そして自分はいいからと差し出された桃城くんの上履きを借りて校舎に足を踏み入れた。
「誰かになんか言われたら俺が誤魔化すんで、合わせてください」
「うん、わかった」
もし先生に見つかったら、そう思うとドキドキするけど、滅多に出来ない体験にちょっとわくわくしてたりもする。
部活なんかで残ってる生徒は部室や体育館に居るみたいで、放課後の校舎にはもうあまり人は居ないみたいだ。
学生として、毎日のように通い過ごす学校という場所だけど、自分が普段見慣れたそれとは全く違う景色に空気。
ただ校舎を歩いているだけなのに、凄い冒険をしてる気分になる。
このまま上手く廊下を切り抜けられるかと思ったとき、廊下の角の向こうから足音が聞こえた。
「あっ」
「千石さん、あんま顔見られないようにしてて」
声をかけようとした俺に桃城くんが耳元で囁きかける。
俺も慌てて口を噤んで頷いた。
リノリウムの床を歩く足音が少しずつ近付く。
そして角を曲がって現れたのは、若い男の先生だった。
俺達の姿を見て少し驚いたような表情を見せる先生に、俺が青学の生徒じゃないと気取られたのかとヒヤリとした。
けれど、どうやら杞憂だったようで。
「桃城、なんでこんなところでジャージなんか着てるんだ?」
「あはは、水飲もうとしたら蛇口捻りすぎて思いっきり水被ったんすよー!傍にいた友達にも引っ掛けちゃって」
「そりゃあ災難だったな。二人とも風邪引くなよ」
ヒラヒラと手を振って先生は背を向けて立ち去り廊下の向こうに消えた。
暫くの間お互いに黙り混み、完全に気配が消えたと思った瞬間俺達は同時に吹き出した。
「ぷっ、あははは!すっごいドキドキしたぁ!」
「俺もっすよ〜!でも上手く誤魔化せて良かった!」
二人で笑いながら廊下を進んでいくと、桃城くんが足を止めた。
「ここっす」
扉を開けて中へと促され、少しの緊張とわくわくする気持ちを胸に秘めて足を踏み入れる。
教室なんて大まかな作りはどこも一緒だけれど、やっぱり初めて訪れる彼の教室はとても特別に見えた。
出しっぱなしのプリントやノートで、言われるまでもなく何処が彼の席かはすぐわかる。
「ここだね、桃城くんの席」
「そうっす!すみません、あと半分なんでもうちょっとだけ待ってください」
「いいよいいよ、ゆっくりで」
「えー!一緒に出掛ける時間なくなるじゃないっすか」
「だってこんなこと滅多に出来ないじゃない?ご飯行くのはまた別の日に行けるしこれはこれで楽しもうよ」
前の席の椅子を借りて向かい合わせに座って、桃城くんの机に肘をつく。
桃城くんはそれもそうかと思い直したらしく笑って頷いてくれた。
「ところで、なんで補習なんか食らったの?」
「小テストの範囲間違えて勉強してきたんすよ〜……」
「あー、なるほど……数学?わかんないとこあったら教えたげるよ」
「マジっすか!?」
「解き方だけね。答えは自分で出すこと」
「うっす!お願いします!」
「うん。証明問題かぁ……解き方はこの例題を元にするといいよ」
教科書を示してヒントを出しながら、桃城くんがプリントに向かう姿を盗み見る。
眉間に皺を寄せて問題を解く姿はテニスの事を考えているときとは少し違う。
こんな風に悩む姿を見るのは初めてで、ちょっと新鮮。
だけどきっと、この学校に通う彼の友人たちはそんな姿をいつでも見られるんだろうな。
授業を受ける姿や休み時間に友達とふざけあう姿、放課後に部活で頑張る姿を。
廊下でばったり会ったりだとか、お昼休みを一緒に過ごしたりだとか、放課後に教室まで迎えに来たりだとか。
同じ学校なら容易く叶うそんな出来事は、俺にとってはそうではない。
桃城くんは素直だ。
いつも真っ直ぐに俺に気持ちを伝えてくれて、会いたいとか傍に居たいとか、俺が拒絶されるのを恐れて伝えるのを戸惑う気持ちを代弁するように言葉にしてくれる。
ちょっとの間だけでも一緒に過ごせる時間を求めてくれる。
だから俺も求められるし、彼もそれに応えてくれる。
学校が違う以上、会える時間に制限があるのはどうしようもないことだとわかってるけど。
でも時々考えてしまう。
桃城くんは、本当はもっと近くにいてくれるような存在を求めてるんじゃないかって。
頬杖をついてプリントに向けて伏せられた顔を見つめる。
そんな視線に気付いたらしく、桃城くんもこちらに視線を向けた。
「千石さん?どうかしました?」
少し物思いに耽っていたのを見破られたみたいだ。
窺うような瞳で見詰められて、思わず考えていたことが口から溢れる。
「……たまにね、思うんだよ。もしも同じ学校だったなら、もっとたくさん君と一緒にいられたのかなって……こうやって、自然に傍にいられたのかなって……」
「千石さん……」
「ね、桃城くんは、俺と学校一緒が良かった……?」
言うと複雑そうな表情で、桃城くんは目を伏せた。
困らせてしまったかもしれない。
「お、れは……それでも……同じ校舎で、一緒に居られなくても……」
桃城くんの声が震える。
伏せた睫毛が小さく揺れて、机に伏せた俺の手に豆だらけの手のひらが重なる。
そして真っ直ぐに、桃城くんの瞳が俺を見据える。
「千石さんが山吹中で、俺が青学で……良かったって思うんです。だって、そうじゃなかったら俺達、あの日、あのコートで戦えなかった……っ!」
その言葉に、引き結んでいた唇が綻ぶ。
「……うん、俺も」
桃城くんはそんな俺を見て瞠目する。
自分の答えが、俺を悲しませるとでも思ったのかもしれない。
だけど、俺はその返事が嬉しかった。
桃城くんも俺と同じ気持ちでいてくれて。
「あの日、あの試合で俺は君と、君のテニスに恋をしたんだ」
あの日、君と戦った事は俺にとって大切な出来事だったから。
君とこうして同じ校舎で過ごす時間は、とても魅力的だけれど。
「だからね、あの日、あの時あのコートで君と出会えてよかった」
桃城くんの表情が緩やかに安堵の笑みに変わる。
「よかった」
溢れるように呟かれたその声から、彼が俺の事も俺との試合の事も大事に思ってくれてたんだってわかる。
もし今、俺と彼との立場が逆でも、俺も同じことを言っただろう。
そして彼が笑ってくれたなら、同じ言葉を溢すと思うから。
ただ、それとこれとは話が別。
今のこの状況は目一杯楽しまないと損だ。
こんなチャンスはきっとそうそうないんだから。
夕日の色に染まる教室で二人きりだなんて。
握られていた手にそっと力を込めて、その目を見つめる。
「でも、このシチュエーションは楽しみたいかな?」
「それは、同感っすね」
意図を察したらしい桃城くんが立ち上がり身を乗り出して俺の頬に手を添える。
それに応えて、俺も瞼を閉じた。
触れあった唇の熱さとか、手のひらが頬を撫でる感触が心地よくて。
桃城くんの首に腕を回して絡む舌に応えると、二人きりの教室に吐息と水音が響く。
互いの息があがってきて、一度唇を離して目を開けると、唾液が緩く糸を引いて夕日の光を反射して煌めくのが一瞬だけ見えた。
「ん……っ」
「はぁ……っ」
俺の唇を桃城くんの親指が拭う。
微笑む彼の顔が優しくて、だけど熱っぽくて。
まだ足りないと思ってるのは、俺だけじゃないんだと嬉しくなった。
「ね、千石さん、もう一回……」
「う、ん……」
再び目を閉じて、桃城くんからのキスに胸を踊らせる。
唇に吐息が掛かって、空気を通じて彼の熱を感じて。
触れる、と思ったその時。
「桃ー!先生がプリント終わったかってー!」
なんの前触れもなく、いや気付かなかっただけであったのかもしれない、けどとにかく唐突に教室の扉が開けられて二人して咄嗟に離れる。
勢い余って椅子ごと飛び退いたら派手な音を立ててひっくり返った。
でもそんなこと気にしてる場合じゃない。
俺の自慢の動体視力はその声の主の顔を瞬時に認識していたから。
そのまま机の影に隠れるように床に四つん這いになる。
「え…………だ、大丈夫?そこの君」
「は、はい……っ、大丈夫、です」
あんまり喋ると声でバレるかもしれない。
でも俺は桃城くんのクラスの友達を装ってここにいる。
“先輩”が心配して掛けてくれている言葉を無下にするわけにもいかない。
心持ち声を変えて返事をしたけど、あまり長い会話はできないだろう。
それにいつまでもこんなところで這いつくばってるわけにもいかない。
でも、顔を見られたら一発でバレる。
「……? ねぇ、そこにいるのもしかして……せ」
訝しむ声に心拍数が跳ね上がる。
これはもう、観念するべきだろうか。
白旗を上げかけた俺を庇うように、桃城くんが身体を俺と彼との間に滑り込ませた。
「あ、あーっ!もう終わります!ありがとうございます、英二先輩っ!てかなんで英二先輩がここに?」
「職員室の前通り掛かったら遅いからちょっと見てきてくれってさ。あと15分くらいで先生来るってよ」
「えっ!あ……マジっすか……ほんともう終わるんでその……これから持ってこうかなと思ってて……っ!」
桃城くんがしどろもどろに言葉を紡ぐ。
先生が来るならそれは今以上にピンチなんじゃないか。
その前に何処かに隠れるか、先に俺だけ表に出ているか。
でも一人で居るときにまた先生に遭遇したら、今度こそ誤魔化せないかもしれない。
必死に頭をフル回転させてると、菊丸くんは事も無げに言った。
「……ん〜、じゃあ俺、先生にもうすぐ来るから職員室に居てって言っといたげるよ」
「えっ!?いいんすか!あっ、ありがとうございます!」
「じゃあ俺行くかんな〜。早く行ったげなよ?」
「はい!よろしくお願いします!」
机の隙間から様子をうかがっていると、桃城くんに振り返った菊丸くんはにっと笑って、心なしか視線を俺に向けた気がしてまた鼓動が跳ねる。
「桃、貸しだかんな〜」
ウィンクをしてひらりと手を振った後、菊丸くんは扉を閉めて立ち去っていった。
扉の前から人の気配が消えると、桃城くんは深く息を吐いて脱力する。
「はぁ〜……っ」
「あ、あれ、バレてたよね……?」
「たぶん……でも、黙っててくれるみたいっすね」
「だね……。見付かったの菊丸くんで良かった、かもね……?」
「っすね」
苦笑いした桃城くんは、床に座り込んだままの俺に手を差し出す。
その手を借りて立ち上がり、すっかり霧散してしまったさっきまでのムードを思い俺も苦笑した。
でも、残念に思う反面ちょっとほっとしてる自分も居る。
あのまま続けていたら、キスだけじゃとても終われそうになかったから。
プリントに目線を向けて本当にあと少しだった残りの問題の答えを書き込むと、桃城くんは筆記用具を鞄にしまった。
「送るんで、出口まで一緒に行きましょう。先に出てさっきの裏庭で待っててください」
差し出された俺の制服が入った体操着袋を受けとる。
「うん……じゃあ、行こうか」
この制服に着替えたら、魔法が解けるみたいにこの時間は終わっちゃうんだと思った。
もう少し一緒に居たかった、なんて思うのは贅沢だろうな。
そんなことを考えながら帰り支度をして扉に向かう俺の後ろから、桃城くんが呼び止めた。
「千石さん」
「ん?なに?」
振り返った俺の唇に、桃城くんの唇が軽く触れる。
「っ!」
「さっきの続き……後でしましょうね」
「……うんっ!」
はにかむように笑って言う桃城くんに、思わず力を込めて頷く。
この服を脱いでも、彼の魔法はまだ解けそうにない。
―終―
2017/03/31 up